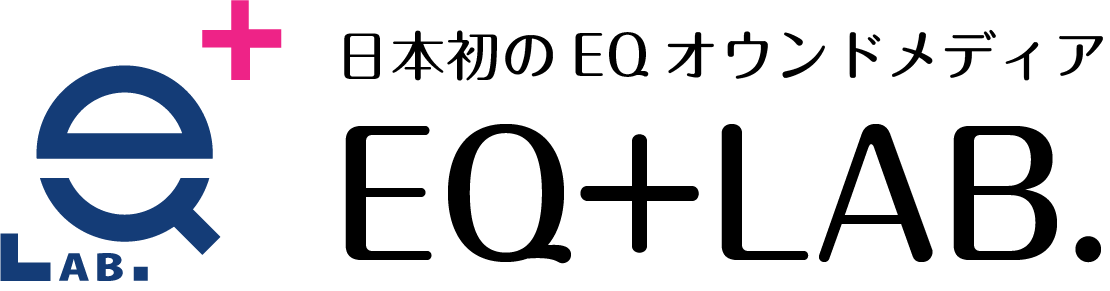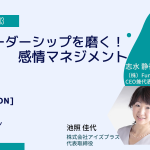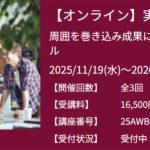EQ+LAB.編集長の杉山です。
このコラムを読んでくださっている方には日経新聞を読まれている方も多いと思います。
EQについて益々注目を集めるようになったのが、今年4月。
「技術や知識では人は動かせない。動かすのは“人の心”だ」
日本経済新聞『私の履歴書』(2025年4月掲載)で、
ソニー元社長・平井一夫さんが語った言葉の数々は、
現代のリーダーシップに欠かせないEQ(心の知能指数)の本質を映していました。
聴く力が、信頼を生む
平井氏のこの記事を読んで行くと、30代のころからEQを自ら実践し体現してきた人なのがうかがえます。
配属先を自分で選べなかった若手時代。
平井さんは「与えられた環境の中で、まず周囲の声を聴くことから始めた」と言います。
リーダーとしての第一歩は、“話すこと”ではなく“聴くこと”。
人の話に耳を傾け、相手の立場や感情を理解しようとする姿勢が、
信頼という土台を静かに築いていく。
これはまさに、EQの中心にある「他者認知」「共感力」。
チームの空気を変えるのは、リーダーの聴く姿勢なのかもしれません。
異見を歓迎する勇気
平井さんが繰り返し語っていたのが、
「異なる意見を歓迎する」というリーダーの在り方でした。
自分の考えに固執せず、現場の声を尊重し、
多様な視点を受け入れることで、チームの創造性は広がる。
EQの観点で言えば、それは“違いを価値に変える力”。
意見がぶつかることを恐れず、むしろそれを糧に変えていく柔軟性。
そこにこそ、組織が生き生きと動き出すアイディアや可能性が生まれて行きました。
「正しい人間であること」が難しい時代に
平井さんは「正しい人間であることが、最も難しく、そして最も大切」と語っています。
成果主義やスピードが求められる時代だからこそ、
誠実さや公正さがリーダーのEQを試す瞬間は少なくありません。
知識やスキルよりも、
「この人の言葉なら信じられる」と思ってもらえる人間性。
EQの本質は、結局そこにあるのだと感じます。
平井さんの言葉を通して、改めて思うのは——
EQは“高ければいい”わけではないということ。
立場や環境に合わせて柔軟に自分を変容させ、
「ありたい姿」に近づいていく力。
それこそが、本物のEQの発揮なのだと思います。
40代、50代の私たちが今こそ磨きたいのは、
共感力、信頼力、そして“部下や仲間の声を聴く力”。
今回の連載には、リーダーとしてだけでなく、
“生き方としてのEQ”のヒントが詰まっています。
是非機会を見つけて平井氏の『私の履歴書』全文も
ご一読ください。
EQ+LAB.編集長
Six Seconds EQプラクティショナー
杉山夕希子
【関連する記事】
EQプログラム導入事例 Diversity&Inclusion文化への挑戦 大手外資系製薬会社 R&Dチーム